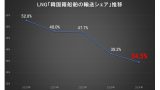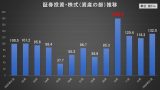サウジアラビアの記者殺害問題が市場に影響を与えているとのことで、「サウジアラビアの動静によって上値が制限されている」などという報道もあります。
日本人は、サウジアラビアという国について石油を多く生産する国である程度の理解しかありませんが、実はサウジアラビアは非常に興味深い存在です。そもそもサウジアラビアという国名が「サウード家のアラビア(王国)」という意味であることをご存じでしょうか? つまり建国者であるアブドゥルアズィーズ・イブン・サウードの一族、サウード家が支配する絶対王政の国家なのです。
しかし欧米世界は、他のアラブ諸国と違ってサウジアラビアとはよりフランクに付き合うかのような柔軟な外交を行っています。これはなぜなのでしょうか?
サウジアラビアがどのような国なのか、湾岸戦争開始前に佐藤大輔御大が述べた文章があるのでそれを以下に引用します。
<<引用ここから>>
■サウド家のアラビア
誤解を恐れずに述べるならば、サウジアラビアとはジレンマの国である。
この国はアラブ的・イスラム的傾向が近代国家にとって有害であることを経験的に知る人物、イブン・サウドによって建国された。だが、国民の圧倒的多数は最も戒律の厳しいワッハーブ派イスラム教徒であり、国内では厳格にイスラム法を適用しなければならなかった。よって、イブン・サウドはその開明的方針を外交政策に限らざるを得なかったのである。
穏健かつ親欧米的な外交政策は、この国の国際的立場を強化した。その莫大な原油埋蔵、産出量だけで判断されるのではなく、アラブ世界で唯一話の通じる相手としての評価も勝ち得たのである。だが、それは同時にアラブ世界における立場の難しさを増す結果にもなった。アラブ世界の勢力もまたサウジを指導的国家として考えているため、思い切った政策を取れなくなったのだ。サウジは、国際社会とアラブ世界の双方に接点を持ったがゆえに、どのような行動を取っても欧米及びアラブの双方から、疑われ、非難される国になってしまったのである。
六○~八○年代におけるサウジの外交政策は、このジレンマの打開が目標だったと言っても過言ではない。イラクのクウェート侵攻まで、サウジはアラブ世界の指導国としての行動を強化することでこのジレンマを解決しようとしていた。それこそが、建国以前から敵対しているイラクを押さえ込む唯一の手段だと彼らは考えていたのだ。
⇒引用元:佐藤大輔『主砲発射準備よし!』(德閒書店)「湾岸危機シミュレーション」P257.
<<引用ここまで/強調文字は筆者による>>
佐藤大輔御大の分析は現在でも通用します。サウジアラビアは、対欧米では柔軟に振る舞い、そのおかげで国益・国力を伸張させましたが、国内そしてアラブ世界に対しては「アラブの盟主的」な振る舞いをしなければならない国なのです。
(柏ケミカル@dcp)