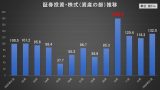読み物的な記事を一つ。
何度も引いて恐縮ですが、本間九介さんの『朝鮮雑記』(李氏朝鮮末期1894年の旅行記)に、現在の日本人からすると、非常に興味深い記述があるのです。
本間九介さんは、今まさに列強の間で滅びようとしている朝鮮を旅しながら、「国が滅びようとしているのに、もっとこう、国の現状を嘆いて立ち上がる人間がいてもいいんじゃないのか」と嘆いています。
朝鮮を滅ぼそうとしている列強の側に日本もいたので、興味深い倒置であり、錯誤感です。列強の魔の手を逃れるべく、明治維新をやってのけた日本人だからこそ抱く感想だったかもしれません。
以下に、『朝鮮雑記』の「慷慨家」から引いてみます。
慷慨家
皇家(朝鮮王家)が末運に至り、二十四郡(朝鮮全土)に更無人との嘆きを発するようになった今、国家が人を育ててこなかったことを悔いても、すでに手遅れというべきであろう。
ああ、かの国の今日は、まさに国家の命脈が絶えようとしているのであって、わずかに列強の権力バランスの上で、かろうじて、ぜいぜいと余命を保っているにすぎない。敵愾の志があるものは、今こそ、剣をとって、起ち上がる時機ではないだろうか。
しかし、韓人は気楽この上なく、朝野ともに(宮廷も民間も)昏々としている(意識がない)。
むやみに春眠を貪る、そのあいだにも、夜来の風雨(外国からの介入や攻撃)は、にわかに落花(国家の終焉)を促進させようとしているのを知らない。
いったい、この状況をどう評すればいいのだろうか。
(後略)⇒参照・引用元:『朝鮮雑記 日本人が見た1894年の李氏朝鮮』著:本間九介,クリストファー・W・A・スピルマン監修・解説,平成28年02月05日初版第1刷発行,祥伝社,pp149-152/以下同
※ルビは原文ママ/強調文字、赤アンダーラインなどは引用者による
朝鮮人が立ち上がらず、能天気に春眠を貪っている――となぜか本間さんが慨嘆しています。
実はこの「慷慨家」はここからが面白いのですが、本間さんのところに崔某という人物が訪ねてきて、自分を日本に連れて行ってくれと懇願するのです。
崔さんは「立志書を読んで数年暮らしてきたが、片田舎に埋もれるばかりで活躍ができない。日本に行って、日本の能力のある人物に接して才学を伸ばして、この国で何かをなしたい」と訴えかけました。
本間さんは、好漢ではないか、この人物は見るべきところがあるかも……と思うのですが、以下のような落ちがつきます。
(前略)
いろいろ話しあってから、最後に彼が言うには、「私の家は、今でこそ落ちぶれているように見えますが、十代前は、領議政を三代つとめたのです。わが父祖のことを思いますと、血の涙がさめざめと流れるのを禁じ得ません。
私は、かつて神明に誓いました。生きて家名を上げることができなければ、死んでも子孫から祀られることはない、不祀の鬼(無縁仏)になるしかないと。
私の志は、このように切実なものです。
あなた様にお願いします。どうか、あなたがたの国にお連れ帰りください。いつか、志を得て、大廈高楼(大きな家)に寝起きし、九鼎(りっぱな器)で腹いっぱい食べることができるようになりましたら、それもすべて、あなた様のおかげしょう」。
ああ、私は彼を買い被っていたようだ。彼はわが国を憂える人ではなくて、わが家を憂える人だったのだ。
(後略)
結局、「日本に連れていってくれ、この国で何かをなしたい」というのは、自分が富貴をなしたい、という話であって、決して衰亡のこの国をなんとかしたい、という話ではなかったのです。
そもそも日本人が「なんとかならんのか朝鮮は」と慨嘆していることが不思議なねじれですが、本間さんは、この崔某という人物にガッカリしたのでした。
日本に留学して学んだ人が「朝鮮をなんとかせねば」と憂国の志をもって帰国・活動するのは、この後のこと(その人たちは現在では親日派としてすっかり否定されています)。
1894年、李氏朝鮮末期の民草にとっては、恐らく「国が滅びるかもしれない」というのは縁遠い感覚だったのでしょう。
(吉田ハンチング@dcp)